 |
|
| トップ物理教育情報教育GPS考古学 | |
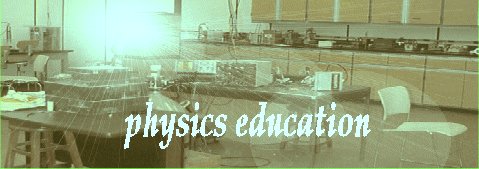 物理の話題エネルギーの発見と筋肉による錯覚についてエネルギー・近くて遠い存在 "我々は横紋筋にだまされている" すべての分野において言えることであるが、”人類の知識や重要な発見は大勢の人間の経験の積み重ねによって得られたものである。” あたかも、力学はニュートンのような一人の天才が現れて,出来上がったように思われがちであるが、物理学においても、上のことは決して例外ではない。 その典型的な例が「エネルギー保存則の発見」である。 エネルギー保存則の発見までの長い道のり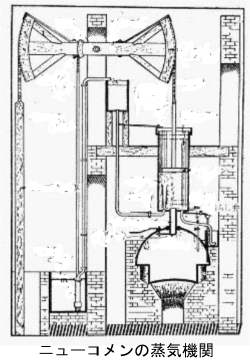 ニュートンの著書「プリンキピア」が出版されたのは、1687年であるが、ヘルムホルツによる理論的な「エネルギー保存則」の定式化は 1847年である。 ニュートンの著書「プリンキピア」が出版されたのは、1687年であるが、ヘルムホルツによる理論的な「エネルギー保存則」の定式化は 1847年である。物理学者が「エネルギー」の重要性を認識するには、ニュートン力学の誕生から、なんと 2世紀近くの歳月を要している。 その間に、ニューコメンの蒸気機関の発明(1712年)、さらに、ジェームズ・ワットによるその改良(1769年)がなされ、この18世紀に、鉱工業の「産業革命」が起こる。 さらに19世紀になると蒸気機関が汽船や鉄道等、交通機関に使われるようになり、急速に熱エネルギーの実用的利用が進んでいった。 ところが、物理学者の方はその間それらに関心を向けず、もっぱら惑星運動を数学を駆使して解く、高邁な「天体力学」の問題に取り組んでいた。 物理学は熱機関の発展にはほとんど寄与していなかったと言える。 しかし、1842年、ドイツ人医師マイヤーによる、転機をもたらす論文が現れる。 それは「熱と仕事の同等性とエネルギーの保存」に関する論文である。 (この発見の経緯は大変興味深い。 それについては、本ページ・末尾のエピソードをお読み下さい。) 機は十分に熟していた、(むしろ遅すぎる!)。 まるで堰を切ったかのように、ジュールをはじめ多くの物理学者達が次々それを検証する実験を行い、熱エネルギー、電気エネルギーを含めた エネルギー保存則 、とりわけ今まで軽視されていた「仕事量」の重要性が再認識されるようになる。 力学においても、ヘルムホルツによって、運動エネルギー概念が明確にされ、 「力学的エネルギー保存則」 および、それをさらに発展させた普遍的な「エネルギー保存則」が力学的見地から理論構築されたのである。(1847年) ここで、「運動エネルギー、仕事概念、および 力学的エネルギー保存則 はそれ以前から知られていたのではないか」 と疑問に思われるかも知れないので、付け加えて置く。 確かに、”運動の勢い”を表す量として、ニュートンの考えた運動量 mv ではなく、同時代の哲学者ライプニッツは初速度 v で投げ上げた物体の高さが v2 に比例することから、運動の勢いは mv2 で表すのが適当だとした。 しかし、彼が「運動の勢い」として考えていたのは mv2 であって、 1/2mv2 ではなかった。 また、それをエネルギー概念として明確に捉えていた訳ではなく、計算上の便宜的な量として考えられていたに過ぎない。( 運動エネルギーとして 1/2mv2 を最初に定義したのはヘルムホルツである。) また、 力×距離 で表される仕事量の方も、てこや滑車の原理である「仕事の原理」として使われていたことは事実であるが、それは、力の釣り合いを扱う「静力学」の分野に留まり、運動を扱う「動力学」では、その重要性の認識はあまりなかった。 それらの重要性 は「エネルギー保存則」すなわち”不滅のエネルギー”概念の誕生を待ってはじめて認識されたのである。 日常感覚の「仕事」と物理用語「仕事」とのずれでは、なぜエネルギーの発見はそれほどまで遅れたのだろうか。私は、エネルギーの基礎である「物理的な仕事」すなわち「力を出して動かす」ということを感覚的・直感的に把握できないという人間の筋肉の特殊性に、その最大の原因があるだろうと考えています。 それに対し「力」の方は、我々は出したときの筋肉の感覚や神経の痛覚を通してその大きさ・強さを実感できるので、「力」は物理的にも理解しやすい。 私自身の記憶を振り返って考えると、高校の授業で、最初に「仕事量=力×動かした距離」と習ったとき、仕事量とは何と「人工的な量」だろうと思った。 力×時間で定義される力積なら、力が働き続けることで与えるトータルな効果を表す量として理解できるが、時間ではなく距離を掛けるのはどんな意味を持つのか理解できなかった。 その上、日常使う「仕事」の意味と、物理の定義がかけ離れているのではないかという素朴な疑問を持った。 たとえば重いものを持って動かさずに立っているだけでも、「仕事」をしたときのように疲れてしまう。 ところが、物理では、動かす距離はゼロなので、仕事=0となる。等々.. そんな疑問を解決してくれたのが数年後に読んだ「ファインマン物理学」の力学の一節だった。 筋肉の特性が仕事の重要性の認識(=エネルギーの発見)を妨げた。私のように、日常用語の仕事と物理学の仕事の違いに戸惑っている初学者のために、その箇所を以下に引用する。 (坪井忠二訳 「ファインマン物理学」(1)力学 第14章 岩波書店)「我々がおもりをもっているときに,“生理学的"の仕事が必要であることは,たしかである。なぜ汗が出るのか? おもりをもち上げているために,食物が消費されるのはなぜか? おもりをもつというだけのためにからだの仕掛けがエンジンをフルに動かしてはたらいているのはなぜか? おもりを机の上におけば,何もしないでも、おもりはそこにおかれたままになっている。:エネルギーを供給しないでも,机は同じおもりを同じ高さに静かに持ちこたえることができる! 生理学的の事情は,次のようなものである。 人間や他の動物の筋肉には2種類のものがある:第1は横紋筋とか骨格筋とかいわれるものであって,例えば我々の腕の筋肉のようなもので,思ったとおりに動かすことができる:第2は平滑筋といわれるものであって,腸の筋肉,あるいはハマグリの大閉殻筋のようなものである。平滑筋のはたらきは非常におそいが、ある位置に“とめ"ておくことができる:すなわち、ハマグリが殻をある位置に閉じておこうとすると、大きな力で外からそれを変えようとしても、 ピクともしないのである。力がかかっても、何時間も何時間もその位置を保って疲れない。ちょうどおもりを支えている机のようなものである。ある位置に“とめ"られた筋肉はそこに一時固定し、仕事なしで、ハマグリも別段の努力もしていない。我々がおもりをもっているのに努力しなければならないというのは、要するに横紋筋の構造によることなのである。 事実はこうなのである.神経の刺激が一つの筋肉繊維に達すると、その繊維はピクリと動いては、緩む。だから我々が何かをもっていると、神経の刺激が筋肉に次々にたくさんやってきて、 ピクリピクリが何遍も起こっておもりを支え、また一方他の筋肉は緩んでいるのである。もちろんこのことは実際にもわかる:重いものを持っていて疲れてくると、われわれはふるえだす。これは、刺激がやって来るのが規則的でなく、その上、筋肉が疲れていてはやく反応しなくなるからである。どうしてこんなに非能率なしかけになっているのだろうか? そのわけはよくわからないが、進化の道程で、速い平滑筋というものができなかったのである。平滑筋ならば、我々はただ立って、国定しさえすればいいのだから、おもりを支えるのにずっと能率的であるはずである。仕事もいらない、エネルギーもいらないということになるはずである。 しかし平滑筋の欠点は、はたらきが非常におそいということである。・・・」. つまり、我々の骨格筋である横紋筋は、動かさないで、力だけを出すときでも、その筋肉を構成しているミクロの筋繊維は、絶えず、ピクピクと縮んだり伸びたり、つまり、筋繊維は、「力を出して、ある距離動く」と云う 「物理的な仕事」 を繰り返している。 このミクロの物理的な仕事のために疲れるのである。 だから、我々の「日常感覚の仕事」と「物理的な仕事」とは、同一のものであり、本質的に相違したものてはない。 とファインマンは述べている。 この非効率な横紋筋の性質は、動物が敏速に動作する必要性から、縮んだら、すぐ次の動作に移れるように緊張を解く=すぐ緩む(だらんと伸びる)ようにできているからである。 力を出し続けるためには、筋繊維はピクピク動き続けなければならないのである。 ファインマンのこの筋肉の解説は、1960年代に書かれたものである。 詳細な現代的な解説は、たとえば、wikipedia (https://ja.m.wikipedia.org/wiki/)「筋肉」 の項を見ていただきたい。 大筋において、ファインマンの説明が正しいことがわかるだろう。 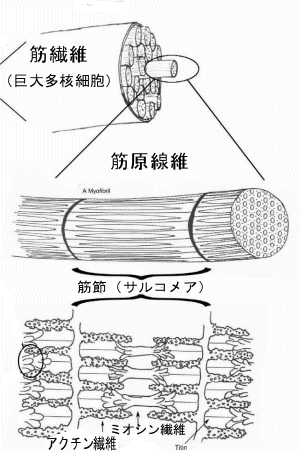 図は wikipedia 「筋肉」 より 人間の横紋筋は筋繊維(巨大な多核細胞)の束から出来ている。さらにその筋繊維は微細な筋原繊維の束から成り立っている。(上図) 筋原繊維はサルコメア(筋節)とよばれる基本単位が縦につながって出来ていて、それを構成するミオシン・フィラメントがアクチン・フィラメントの中に入り込むことにより筋原繊維は収縮する。 その際、エネルギー源となる高エネルギー分子ATP(アデノシン三リン酸、エネルギーはリン酸分子中に静電エネルギーとして蓄えられている)を消費する。 収縮の分子レベルの詳細なしくみはまだ解明されていない。 我々の筋肉の性質によって、「力×距離で定義される仕事」をすることと、「動かさないで力だけ出す」ことの区別がつかないのである。 この錯覚のため、「力」が本質的に重要な量であり、「仕事」は副次的な「学問上の量」であると考えてしまう。 実は、逆であって、力だけを出すのは、机という無生物でも大きな力を出せるのであって、「力」は物理的にはあまり重要ではない。 「仕事」の方が、はるかに重要である。 もし、我々の骨格筋がエネルギーの無駄の多い横紋筋ではなく、平滑筋で出来ていたなら、 「力だけ出すのなら何でもない。しかし、力を出して動かすのは大変なことだ。」 と感覚的に実感できただろう。 そして、エネルギーと、その保存則の発見は、ずっと、早まっていただろう。 もちろん、ニュートンも、その後継者たちも、このことには全く気付かなかった。 それ故、力や力積を原因とする運動の理論 「ニュートン力学」を作り上げたわけである。 最初に述べたように、歴史的に見て、仕事の重要性に気付くのに、「ニュートン力学」の誕生から、約200年もの歳月を要した最大の理由はそこにあると、私は考えている。 「物理学者達は筋肉の錯覚に惑わされてきた」と言えるだろう。 仕事はロボットでイメージしよう。それゆえ、仕事をイメージしたいときには、人間をロボットに置き代えて考えるのが良い。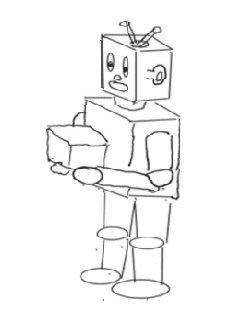 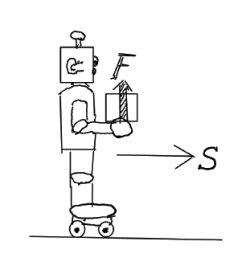 図 1 図 2 図1のようにロボットが荷物を持って立っているだけなら、ロボットの電源を切っておけばよい。 しかし、荷物を持ち上げるには、電源を入れて、「ウィーン」とモータを動かす必要がある。 つまり、仕事をするにはエネルギーが要ることがわかるだろう。 今度は力と動かす向きが90度異なる場合を考えてみよう。 これは簡単である、 図2 のように、ロボットの足にローラスケートのような車を付ければ、荷物を持った状態で、軽く横滑りさせることが出来る。電源を入れる必要もない。 つまり、ロボットが力を出し動いても、動く向きが力の向きと垂直なら、力によるエネルギー消費はゼロ、 すなわち「力のする仕事はゼロ」である。 もちろん移動に際して摩擦があれば、ゼロではない。 しかし、この摩擦は工夫すれば、いくらでも小さくできる。 上の例では、その目的で車輪を使った。 力と移動の向きが異なる場合の仕事の計算は 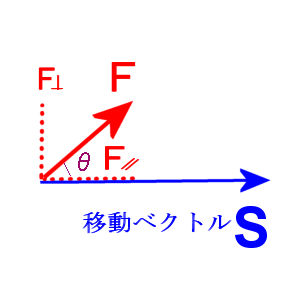 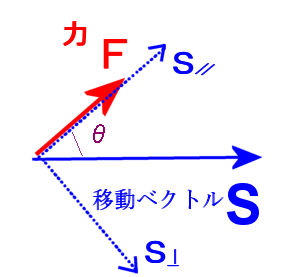 図 3 図 4 1.力のベクトルを移動の方向に平行な成分と垂直な成分に分解して、(図 3) 仕事=移動と平行な力の成分×移動距離 とするか、 あるいは、 2.移動ベクトルというものを考えて、それを力の向きに平行な成分と、垂直な成分に分解して、(図 4) 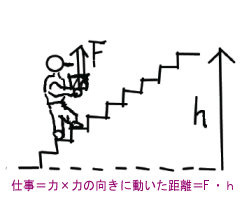 仕事=力×力の向きに動かした距離 とするか 場合に応じて、臨機応変に考えたらよい。 例えば、階段を使って荷物を持ち上げる場合は 2 を使えばよい。 いずれも、数学的には、力のベクトルと移動ベクトルの内積 W = F・S・cosθ であり、変わりはない。 転がり摩擦について シュメールの戦車 (紀元前2500年頃) 余談になるが、人類最古・最大の発明は、車輪の発明だろう。 何と紀元前3500年頃にはすでにメソポタミアのシュメール人よって、発明されていたと云われている。 これによって重力に邪魔させれずに、重い物も楽に水平移動させることが可能になった。この発明はユーラシア大陸の各地に伝わったが、新大陸の原住民には知られず、インカ帝国では、荷物は人の背か、ラバの背中に乗せて運ばれていた。 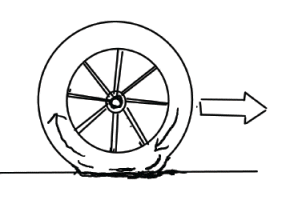 車輪の転がり摩擦は、滑り摩擦に比べて格段に小さく、車輪と路面が接触する部分で荷重によって、双方が変形することによって生じる。 この変形をできるだけ小さくすることで、摩擦をより低減できる。自転車のタイヤの空気圧を高めると軽く走れるようになるのは、そのためである。 鉄道は剛性の高い鋼鉄製の車輪と鋼鉄のレールを使っているため、最も転がり摩擦が小さい。 ただ、昔から車軸と軸受けの間の摩擦の存在が最大のネックであったが、ここでも、軸との間に小さな鋼球を入れて、その転がりで摩擦を小さくするボール・ベアリング軸受けの発明により、その問題もほぼ解決された。 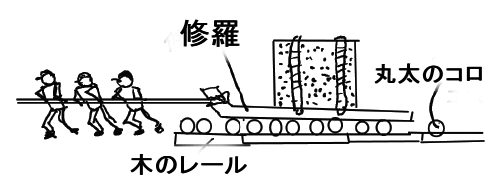  ボールベアリングの原理は車輪よりコロに近い。 我が国では、車よりコロの方が歴史は古いと思われる。 古墳時代に巨石を運搬するのに使われていた。 修羅とは、ソリではなく、巨石を載せてコロで運ぶための台座である。 写真は法隆寺・若草伽爛の礎石をコロで運ぶ様子。(昭和初期) 私の別ページ、筋違道の研究「法隆寺の若草伽藍の礎石の話」を参照。 「骨」 --ー 重力に抗するしくみ ーーー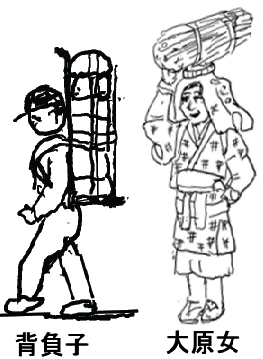 以上、本題から脱線したが、元に戻り、我々が筋肉にだまされているために普段見落としている大事なことを、述べておきたい。 残念ながら、我々の身体には車輪のような便利なものが備わっていない。 そのため、地上の生物は常に「重力」と云う強力な力の作用を受けているので、それに対抗する手段を持たなければならない。 筋肉では、上述の理由で、支えるだけで「疲れてしまう」ので、無理である。 陸上動物が重力に対抗するために備えているのが、頑丈な骨格、「骨」である。 立っているときは、ほとんど筋肉を使っていない。 荷物を担ぐときでも、その重みが脊椎にかかるように、「背負子」を使い、荷をできるだけ高い位置に背負うと楽である。 あるいは、京の「大原女」のように、荷持を頭の上に乗せると楽である。 手で荷物を持つときも、腕を下に垂らし手にぶら下げて、重力が腕の骨にかかるようにしている。 ・ 骨をうまく利用する。 「介護の方法」というテレビ番組を見たが、ベットから車イスに移動させるときは、介護する人もされる人も、荷重がそれぞれの足骨にかかるように、うまく工夫していた。 ・ 腰痛について しかし、変に、脊椎に負担をかけると腰痛の原因になるので、注意しなければならない。 たとえば、椎間板ヘルニアでは、通常腰の部分の腰椎は少し前の方に(腹の方に)カーブしているが、このカーブがきつ過ぎると椎骨をつなぐ軟骨である椎間板の後側が押しつぶされて、脊椎の後ろを走る神経束に触れて痛みがでる。 腰痛が出ないようにするには、腹筋を鍛えるか、コルセットを締めて、この湾曲を小さくすれば、脊椎に荷重をかけても大丈夫である。 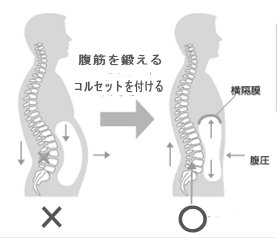 以上のように、普段見落としている骨の役目を物理的に再認識して、生活の知恵とすることは重要である。 補足: 陸上生物が硬い背骨を備えたもう一つの理由は、海中生活では、豊富にあったミネラルが容易に得られなくなったので、代わりに骨に蓄えるようになったからである。 魚でも、タイのような硬骨魚は、進化の過程で、一時期、海から、川などの淡水域に生活する淡水魚に変わり、(淡水ではミネラル分が少ないので、骨に蓄えた) それが再び海に戻った魚である。 それに対して、サメなどの軟骨魚は、元の海に住つづけている魚である。 筋力トレーニング以上、我々の筋肉の特性の欠点ばかり述べたが、逆にその特性を利用して筋肉を鍛えることが出来る。つまり、動かさずに大きな力を出し続けることだけで、筋肉を鍛えることになるのです。 たとえば、相撲の稽古法に突っ張り稽古がある。それは動かない鉄砲柱と呼ばれる柱に向かって、思い切り押す練習である。これで腕と足の筋力が鍛えられる。 また、ラグビーのスクラム練習も同様である。これがラガーの強靱な筋力と体を作るのに役だっている。 また手の握力も、物を掴んで強く握り締めることで鍛えることができる。 ◎ マイヤーがエネルギー保存則を発見した経緯についてマイヤー  ドイツ人医師マイヤーは、オランダ船の船医として、1840年、東インドへの航海に出航する。喜望峰を廻り、赤道洋上で、病気の船員の治療のため、静脈血を抜いたところ、真っ赤な鮮血が出たので驚いた。 ドイツ人医師マイヤーは、オランダ船の船医として、1840年、東インドへの航海に出航する。喜望峰を廻り、赤道洋上で、病気の船員の治療のため、静脈血を抜いたところ、真っ赤な鮮血が出たので驚いた。通常、酸素を多く含む動脈血は真っ赤であるが、体内を巡って戻る静脈血は途中で酸素が消費されるため、血液中の赤血球のヘモグロビンから酸素が奪われて、赤黒い色をしている。 しかし、その静脈血が真っ赤なのはなぜだろうか? 信じられないかも知れないが、マイヤーはこの謎を解くことで、エネルギー保存則を発見したのである。 読者諸君は、マイヤーはどう推理してエネルギー保存則に思い至ったのか、分かるだろうか? 彼はこう考えた。 通常、赤黒いはずの静脈血が、真っ赤であるのは、全身を血液が巡って、戻って来ても、途中で酸素が消費されないことを示している。 故国のドイツでは、じっとベットで寝ている患者でも、静脈血は赤黒い。つまり運動をしなくても、酸素を消費する。 ところが、赤道洋上で、同じく寝ている患者では、酸素の消費が少ないことを示している。 どこに、この差を生じる原因があるのだろう? 彼はその原因は気温差にあると考えた。 北国のドイツでは、気温は体温より低い。 そのため、体温を維持するため、寝ていても、発熱しなければならない。 ところが、赤道洋上では、日蔭におれば、心地よい温度であり、体温を維持するために、発熱する必要がない。 このことが、差を生む原因だと気が付いた。 ところで、体を動かして仕事すれば、酸素が消費されることは、知られていた。 それならば、「体を動かして仕事をすることと、熱を発生することは、同じことではないだろうか」。 と思い至ったのである。 彼は、故国に戻ったのち、精力的に「熱と仕事の関係」を調べて、それらは等価であることを実験的に確かめた。 つまり、熱が仕事に変わったり、仕事が熱に変わったりしても、それらの総量は不変であると云う「エネルギー保存則」を発見したのである。 そして、この結果を論文にまとめて発表した。(1842年) 前述したように、この後、すぐ多くの実験家によって、様々な検証実験が行われ、特にジュールは、当時すでに知られていた電流による発熱量の精密測定から、1cal=4.19J という熱の仕事当量の値を得た。 さらに、1847年には同じドイツ人医師であった、ヘルムホルツは力学理論として「力学的エネルギー保存則」の明確化を行い、すべての形態のエネルギーも力学的エネルギーに還元し得るとし、理論的立場から「広義のエネルギー保存則」を確立した。 エネルギー保存則の発見者であるマイヤーもヘルムホルツも元々物理学者ではなく、共に医師であったことは皮肉である。 このページのトップへ |
・物理教育序論 ・慣性力について(慣性力序説) ・慣性力はみかけの力ではない。(慣性力続編)更新 ・慣性力対話(1)みかけの力とは、ダランベールの原理 ・慣性力対話(2)コリオリの力はみかけの力か NEW! ・エネルギー保存則と慣性力 (慣性力対話 3) ・力はベクトルか?(力の正体をさぐる。) ・開口端で音波はどのように反射しているのか。 ・物理”診断テスト”と”運動についての常識概念” 物理実験・新方式の「運動法則の実験」
ご感想等 |