 |
|
| トップ物理教育情報教育GPS考古学 | |
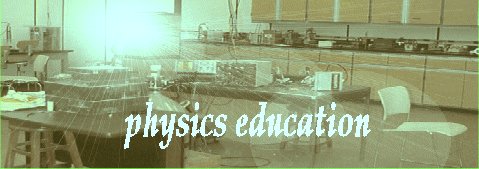 力 学 系 と し て の 電 磁 気 学( MAX.PLANCK の 「理論電磁気学」 を読む )◎ は じ め に ここで、紹介するのは、量子論の創始者、作用量子の発見者として名高い M・プランク の著した 「理論物理学汎論」 Einfuhrung in die Theoretische Physik シリーズ中の1冊 「理論電気磁気学」 Einfuhrung in die Theorie der Elektriztat
und des Magnetismus を、 これまた有名な、寺澤寛一氏が昭和の始めに翻訳して出版されたものである。
ここで、紹介するのは、量子論の創始者、作用量子の発見者として名高い M・プランク の著した 「理論物理学汎論」 Einfuhrung in die Theoretische Physik シリーズ中の1冊 「理論電気磁気学」 Einfuhrung in die Theorie der Elektriztat
und des Magnetismus を、 これまた有名な、寺澤寛一氏が昭和の始めに翻訳して出版されたものである。マックス・プランク は云うまでもなく、長年ドイツ・ベルリン大学の教授を任め、幅広い古典物理学の知識を持った20世紀始めの物理学界の重鎮であり、権威であった。 ◎ 他に類のない電磁気学の書 電磁気学の書物は数多いが、この本の際だった特徴は、その巻頭の1、2章において、他の量の定義に先立って、まず最初に電磁場のエネルギーを定義し、それと、エネルギーの原理(局所的なエネルギーの保存則)のみを用いて、マクスウェルの方程式を導き出して見せる点にある。 また、電磁気学の様々な単位系もこのエネルギーと電磁場を結びつける係数の決定の仕方の相違に過ぎないことを明らかにしている。 このような視点から電磁場を解説した書物は、寺澤寛一氏が巻頭言に述べられているように、他に類はなく、貴重なものである。 しかし、現在この本を手に入れることは勿論、見ることすら困難だろうと思われるので、その一部だけでも紹介しようと考えた。 この解説から、電磁気学を、力学とは区別された独立した分野ではなく、むしろ、電磁場を ”エネルギーを持った場の力学系”として捉え得ることが分かるだろう。 また、拙文の 「おわりに」 で述べるように、本書は20世紀に入ってから「歪曲化された近接作用論」に対する、批判の書であり、 ”近接作用論の再生”を意図したプランクの試みと捉えることも可能だろう。 ここで紹介するのは、全12章(§1〜§102)からなる同書の最初の1、2章(§1〜§9)である。2章以降の紹介は量も多く、他の電磁気学の教科書と大差ない内容も多いので割愛した。 その重要な最初の1、2章は、私が書き直して 別のPDF(PDFはこちら) とした。 内容を詳しく知りたい方は、そちらも お読み下さい。 ただし、元の旧仮名遣い、旧漢字は、現字体に改めた。 また、数式中のドイツ文字は、馴染みがないと思われるので通常のラテン文字に直した。 しかし、文語調の訳文体は、原訳者に対する敬意と、また戦前の書物の香りを残すため、変更を最小限に留めた。 そのため、読みにくいと思われるが、原著者プランクの説明は丁寧かつ教育的であり、通読する読者は、その労に倍加する益を得るだろう。 内容の要約§1 物理学における電磁気学の位置と特徴まず、物理学のあらゆる部門:音響学、光学、熱学等は残らず力学と電気力学に帰着することを述べた上で、その2分野を架け橋するのが「エネルギー保存の原理」であり、本書ではこれをまず第一の出発点とすることを述べている。◎ 媒達作用(近接作用)の原理 つぎに第二には、マックスエル理論の特徴である「媒達作用の原理」を採用することを述べている。 いわく、 『この原理に従えば局所的の事件が多少でも離れた場所に即座に、途中に介在する物体をも飛び越えて現れてくるような事は決してありえない。 むしろ原因となる作用はすべて有限の速度をもって、空間を点から点へと伝搬して行くのである。 故にある場所において、ある時刻に現れる事件は、その直ぐ近くの場所に、その直ぐ前の時刻に起こった事件に依って完全に、かつ一義的に決定されるのである。』 『この理論の他のすべての理論より卓越しているゆえんは、この理論がより決定的でかつ簡単だからと云うのである。』 第1章 電場および磁場の強さ §2 電場の強さ、電気エネルギー通常、まず電荷および電荷量を定義した後、電荷が受ける力から、電場の強さを定義するのだが、それと異なり、プランクは別の方法で電場の定義を行う。電荷の単位の決定には様々なやり方あるので、その決定に代わるものとして、電荷ではなく、電場の強さそのものを、電場のエネルギーから直接定義しようとする。 つまり、媒達作用の原理を認めるならば、当然、電場と云うエネルギーをもつ何らかの力学的存在を認めざるを得ない。 そのエネルギーという力学的量を用いて電場の強さを定義しようと云うのである。 曰く 『電場が幾らかの量のエネルギーを貯蔵して居る事は、電場が物体に運動を起させ得るのを以って見れば明かな事である。何故かというに、弾性体が変形のエネルギーの供給を受けて運勤し出すのと同様に、エネルギー保存の一般原理に依れば上述の運動のエネルギーは必らず電場の電気エネルギーのみに依って供給されねばならぬからである。』 そこで、プランクは、実験的に正の帯電体が受ける力の向きで電場ベクトルE の向きは定義できるが、その強さE には定義の任意性があるので、それを単位体積当たりの電場のエネルギー即ち、電場のエネルギー密度と関連付けて定義する。 つまり、電場のエネルギー密度は  として、ベクトルE の大きさを定義するのである。(註:本書では非有理化単位系を使うので分母に4πを付けている) ここで未知の比例定数として電媒定数εを導入する。(εの値は採用する単位系の取り方に関係することが後ほど示される。) 曰く 『電場の起って居る空間内の無限微小部分に含まれた電気エネルギーと、その体積との比を電場の“電気エネルギー密度”と云う。これは力学的単位で表わし得る量で、もし電気的に中性な電場のエネルギーを 0 と置けば、これは正の量である。これに因んで電場の強さの絶対値の定義を下そうと云うのであるが、その為に今電気エネルギー密度は電場の強さの自乗E2に比例し、かつ同時に“電媒常数"という媒質(例えば空気)の物質的性質のみに関係せる正の比例係数εに比例すると置く,ただし電媒常数の定義はここでは未だ保留して置く。』 『つまり、電媒定数εなる均質物体内における任意の電場のエネルギーの総量は、その物体の体積素片をdτで表せば、 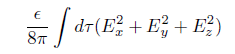 (2) (2)となる。』 プランクは電荷をさて置き、場を直接定義していることに、読者は注目して欲しい。 §3 磁場の強さ、磁気エネルギー、電磁場電場の場合と同様な方法で、磁場 H の向きと磁場の強さを定義する。即ち、 『小さな磁針を用意して、そのS極からN極の方へ向いた向きを、磁場ベクトルHの向きと定義する。つぎに、試験用の磁針に作用する回転能率の大きさは磁針の性質に依るものであるから、これから磁場の強さHの絶対値を決定するわけに行かぬ。そこで我々は、磁気エネルギーの密度を  に等しいと置き、このエネルギーから、上述の絶対値の大きさを定義する事とする。ただし、上式のμ、即ち物質の”誘磁率”はある正の比例定数を表す。』 『そこで、一定の誘磁率μを持った物体内における任意の磁場のエネルギーの総量は 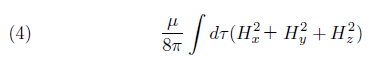 となる。』 次に、プランクは電磁気学とはこの2種の”場”の振る舞い方を探求する学問であると述べる。 (言外にマクスウェルやファラデーの考えに近い”場一元論”ともとれる立場が垣間見られ、興味深い。) 曰く 『一般の場合には場は電場と磁場との両方の作用をなすので、かかる場を 電磁場 と云う。この場の内の各点に於ける電磁的状態は互に全く無関係な2つのベクトル E 及び H に依って表される: 従ってまた電磁場のエネルギーの総量は(2)式及び(4)式の和として決まって来る。 この意味に於いて宇宙全体はただ一個の電磁場であり、すべての電気的及び磁気的現象は皆この電磁場の変化に外ならぬ。 かくして理論上の一般問題は。結局,空間のあらゆる点に於ける電場及び磁場の強さが、ある任意の時刻に於いて与えられた場合に、これからそれの時間的変化を計算する事に帰着してしまう。』 第二章 電磁場の法則 §4 電磁エネルギーの流れ電磁場の微分方程式は、「エネルギー保存の原理」と「媒達作用の原理」の2つから比較的容易に導き出せると述べて、そのために、まず2つの原理から当然の帰結として”エネルギーの流れ”という概念が生まれることを述べる。曰く 『今電磁場の起っている永久に静止せる均質物体内のある任意の部分を促えて考えよう。 エネルギーの原理に依れば、この部分内の電磁エネルギーは、この部分内と外部の物体との間にエネルギーの交換が起るか、又はこの部分内に於ける他の型のエネルギーが変化を起すかに非らずんば、変化する事は出来ない。 先ず最初に述べた場合、即ち外部からエネルギーが這入って来るか、又は周囲に向ってエネルギーを与える場合について考えよう。 媒達作用の原理に依れば如何なる場合にも、問題の部分内のある場所に電磁エネルギーが周囲のある場所から飛び越えて這入って来る事は不可能で,常に連続的の流れとなって外郎から問題の区域内に、その表面を過通して漸次に這入って来るよりほかはない。 故に周囲とのエネルギーの交換は,あたかも流体の流れに似た,空間の表面を通過するエネルギーの流れに依って支配される。 そして各点に於けるこの電磁エネルギーの流れはその場所の電磁的状態、従ってその点の E 及び H の値に依って完全に決定される。』 そして、エネルギーの流れはベクトル量として表すことができることを説明する。 即ち、 面素片 dσ をその法線 ν の向きに流れるエネルギー流量は dσ、dt に比例するから、これを  と置く。 簡単な考察( pdf本文参照 )から、この流れの密度 Sν は各座標軸に垂直な微小面素片を流れる同様な流れの密度 Sx, Sy, Sz を使って , 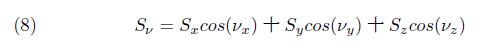 (ここで νx、νy、νz は法線 ν が座標軸となす角) と表される。 これはエネルギー流量密度 Sν は3成分 Sx, Sy, Sz を持つベクトルと見なせることを示している。 §5 ポインティングの法則プランクは、このエネルギーの流れ S と電磁場の強さ E、 H との関係は、本書で最初に登場する経験法則、「ポインティングの法則」として与える。曰く 『エネルギーの流れ S が電磁場の強さ E 及び H と如何なる閲係があるかは経験に依って結論すべき事柄である。経験に依れば、此の関係は極めで簡単な法則に依って支配されるのであって、我々はこの方面に於けるあらゆる経験を集めた総括的の命題としてこの法則を電磁場の方程式を導き出すに当たっての冒頭に置く事とする:それはエネルギーの流れに関する”ポインティングの法則”と云い,曰く、 S は E と H とのベクトル乗積に比例するというのである即ち: 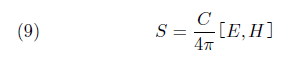 (註: [E,H]はベクトルE、H の外積を表す記号である。) あるいは,同じ意味で: 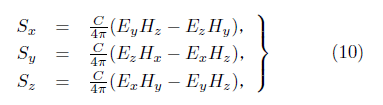 ここに C はある比例常数で,その値は E 及び H の単位の選び方に関係する。』 多くの教科書のように ”ポインティングの法則” を他の法則から導く二次的な法則とはせず、 場のエネルギーの流れを表す基本法則、あるいは基本量として扱っていることに注目して欲しい。 ここでもやはり、電荷や磁荷ではなく、場およびそのエネルギーを主役として捉えている。 §6 電場及び磁場の接線成分に関する境界条件今までに3つの関係、電場のエネルギー密度と E の関係式、磁場のエネルギー密度と H の関係式、電磁場のエネルギーの流れの密度とベクトル E、H との関係式、が登場したが、それらの関係式でそれぞれ未定の係数、ε、μ、C が存在する。よく考えてみると、この内の2つが決まると残りの1つが決定されるはずである。 例えば、ε と μ を決めると電場、磁場の強さ E、H が定義できるので、その E、H を用いてエネルギーの流れの密度が決定され、”ポインティングの法則”の係数 C が決まる。 曰く 『従って上の三つの係数のうち,二つは之を任意にきめて宜しく、そうすれば之に依って残りの係数を三つのエネルギーの式に依つで完全に定義する事が出来るのである。 各媒質に就き、この定義は他の媒質に無関係に採って差支えないのであるから,上述の議論は各個々の媒質につき別別に当て嵌めて宜しい。 さて種類の異なった媒質の間の関係は如何かというに、先づ、媒質の種類が異なって居てもエネルギーの流れに関する比例常数 C は皆同じ大きさであるとするのが好都合である事が従来わかっている。その様にきめると便利であるという事は,若しそう採れば異なった二つの媒質間の境界面に於ける限界條件の形が簡単になるという事から直ちに頷かれるのである。』 そしてエネルギーの流れの連続性から、2つの異なる媒質の境界面での境界条件を考察している。(pdf参照) §7 単位およびディメンションつぎに、プランクは、場のエネルギーとその流れの観点のみから、電磁気学で登場するすべての c.g.s単位系 を見事に整理してみせる。読者はこのことから、プランクの場のエネルギーの観点が電磁気学に於いて本質的に重要な視点であることに気づくだろう。 これも巻頭言で寺澤寛一氏が述べているように他書には見受けられない本書の特長である。 上の§6で、述べたように、電場のエネルギー密度の式  磁場のエネルギー密度の式  および、エネルギーの流れの密度の式 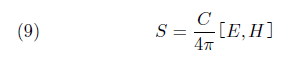 には3つの未定の定数 ε、μ、C があるが、上述のように、この内2つを勝手に決めたら残りの1つが決定する。(つまり、2自由度をもつ。) ここで単位の基準の媒質として、”絶対真空”を取る。 曰く 『今その基準の媒質として所謂絶対真空を採用しよう。 之は又“純粋のエーテル"とも云う。 もっとも自然界には絶対真空は実在しない: 絶対真空に最も近い媒質即ち天体間に介在する空間でさえも、到るところ確かに物質の残痕が浮かんでいる;。 然るに電磁学の種々の経験から確証された最も重要な事実の一つとして,物質に乏しい空間を漸次に稀薄にして行けば其の空間の電磁的性質はついによく指定し得る而も残存せる物質には全然無関係な一定の確然たる極限に近づくという事がわかって居る。 そこでかかる極限的性質を持つ媒質を指して絶対真空と呼ぶのである。』 その真空での値を ε0, μ0 と書くことにする。(常数 C は異なる媒質の境界でのエネルギーの流れの連続性から、総ての媒質で同一であるので、添字をつける必要はない。) この3つの内のいずれの2つを 基準の値=1 と採るか、の違いにより、3種の単位系が生じることになる。 曰く 『真空の電媒常数を ε0、誘磁率を μ0 とする;但し常数 C は総ての媒質につき同一であるから之には脚符を附けない事にしても宜しい。 此の三つの常数の内で二つは任意に何とかきめて宜しい。従って今是等を=1 と置こう。そうすると第三の常数も其れからきまって来る。 さて上述の如き二つの常数としては何れを選ぶべきかというに, ここに三つの異った場合が可能になる。而して此の事から古典的の三種の電磁単位系が出て来る。』 1..ガウスの単位系 ε0=1、μ0=1 と定める。 こう決めると、第3の定数 C はある値になるが、この定数は速度のディメンションをもつことが分かる。(計算はpdf参照) この定数を c と書き、”臨界速度”と呼ぶ。(これは後に、真空中の光速度であることが分かる) 2..マックスエルの静電単位系 ( ’を付けて表すと) ε'0=1、C'=1 と定めた単位系である。 当然 μ'0 は 1 以外の定数となる。 3..マックスエルの電磁単位系 ( ”を付けて表すと) μ"0=1、C"=1 と定めた単位系である。 ( 詳しくはpdf本文参照。 この他 実用単位、有理単位についての解説もある。) 以上のように、複雑に見える単位系の相違も場のエネルギーの観点に立脚するなら、見事に整理できることが分かる。 またこの節の終わりにプランクは、電磁気のディメンションについても、興味深い発言をしている。 曰く 『一定の物理的の量を二種の単位系で表わすと其の数値のみならずディメンションまでが違うという事はしばしば論理上釈明を要する矛盾であるかの様に思われ,中んづく一つの物理的の量の“本当の"ディメンションは何であるかという様な質問をよく提起され勝ちである。 かかる質問は或る対象物の“本当の"名称は何であるかという事以外には何等意味の無い質問であって、ここまで論述を進めて来た際、今更特に其の理由を表明する必要もあるまい。』 §8 ジュール熱以上は、(電荷を除外して!)場のエネルギーに基づく電磁場のいわば、定義に関連する議論であった。 いよいよ、電磁気学の基本法則であるマックスエルの方程式を導く訳であるが、そのためには当然、電流という、場以外の実体を取り扱わざる得ない。ところが、プランクはそれを巧妙に避けるのである。 場のエネルギーの観点からは、電流は場のエネルギーの消費者として現れる。 つまり「ジュール熱」として、場以外の熱エネルギーに転換させ、場のエネルギーを消耗する何者かに過ぎない。 その何者か(=電流密度)は、その場所の電場 E に比例し、そのエネルギー消費率は電流密度×E に比例するから、結局、場のエネルギーの消耗率は E2 に比例し (つまり、その場所の電気エネルギー密度に比例し)、かつその場所の物質の電気伝導の性質に依存することになる。・・これは、私の”勇み足”の説明であって、プランクはただ単に、以下のように経験則として述べる。 曰く 『§4に於いて一物体内に所有せる電磁エネルギーの変化に対する原因を二つ挙げたが,今そのうちの第二即ち:他の型のエネルギーに転換する事に就いて述べよう。 此の方面に関する過去の総べての経験を簡単な一個の定理に纏めると次の如くなる。 即ち:あらゆる媒質内に於いて:電気エネルギーは絶えず到る処で熱に転換しつつあって,而も時間素片 dt の間に媒質の任意の体積素 dτ 内に於いて熱に変って行くエネルギーの量は,其の瞬時に於ける其の場所の電気エネルギーの密度に比例する 即ち: 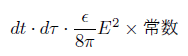 に等しい。 此のエネルギーの量は”「ジュール」熱”と称せられ, 此の現象は,変形し得る不完全な弾性体の内部で弾性張力が次第に衰えて行く場合に弾性エネルギーが熱に移り行く現象と類似している事に着目すれば、いくらかその様子が了解出来るであろう。 ディメンションの上からの簡単な考えに依れば、上式中に含まれた媒質の性質に関する比例の常数は時間の逆数を表わすことがわかる: 依つで之を 2/T と置く事とする。こうすると「ジュール」熱は: 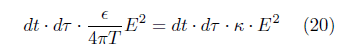 である,但しここに: 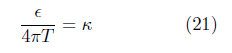 とした。 T が大ならば大なる程,電気エネルギーの消費は緩慢に行われる;此の理由で T をまた其の媒質の“弛緩時間゛とも云う。 T は金属ではすこぶる小さいが、気体では非常に大きく,絶対真空では T=∞ となる,即ち真空内に於いては,あたかも完全弾性体内に於ける弾性張力の場合と同様に,電気エネルギーは永久無限に存続し得るのである。 磁気エネルギーに閲しでは,弛緩現象に似た現象は存在しない。』 §9 マックスエルの根本方程式こうして、プランクは場一元論の観点から、電流を単なる場のエネルギー消耗体とみなしてしまう。一見、この扱いで良いのか、疑問に思えるが,、つぎに示されるように、これらから、手品のように、何とマックスエルの方程式が導けるのである。 この節は本書の核であるので、省かず引用する。 曰く 『さでこれで§4に述べた考察法を進める準備が調ったから之から、いよいよ一般の電磁場の方程式をエネルギー原理に立脚して導き出そう。 均質な物体内の任意の体積部分内に存在せる電磁エネルギーが時間素片 dt の間に受ける変化は(2)及び(4)に依り 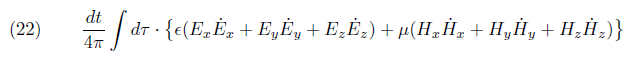 である。 此の変化を起こさせる原因の第一は同じ時間内に此の領域の表面を貫通して外部から内部へ流れ込むエネルギー(5)に依るもので,その総量は:  である。 原因の第二は同じ時間内にそこに生じた熱量(20)に依るもので,その総量は : 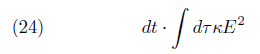 である。 而して(22)式は(23)式から(24)式を減じた差に等しくなければならぬ。 そこで表面積分(23)を体積積分に転換すれば: 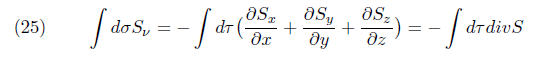 となり、 次に総べての量を方程式の左辺に移項して唯一つの体積積分に纏めて考えると,上の体積は幾らでも任意に小さいものを採っても宜しいという理由に依り、τ の掛かって居る量は 0 にならねばならね事がわかる。 斯くて: 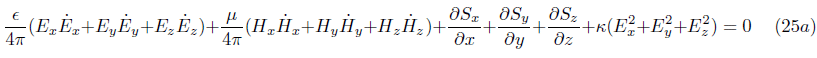 を得る,此の中のエネルギーの流れのベクトル S は(9)に依り 「ガウス」の単位系で表わせば: 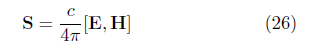 で与えられる. 此の一般に成立すべき方程式(25a)は6つの電場磁場の強さ及びそれ等の導函数(或は微(分)係数ともいう)に関して同次の2次方程式になって居る。 此の式から電磁場に関する6つの同次の一次微分方程式を出そうというのであるが,それには此の式の中に於ける6つの電場磁場の成分 Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz の掛かって居る量を各々 0 に等しいと置けば宜しい。 その様にして6つの方程式: 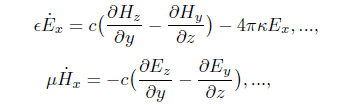 が得られる,あるいは之をベクトルの形で表わせば : 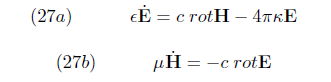 となる。 これが静止せる均質で等方な物体内の 電磁場に関する「マックスエル」の根本方程式 である,かかる物体に於ける電気的並びに磁気的現象に関する法則は,後で示す通り,皆此の方程式と限界條件(11)とから−価的に導き出されるのである。 簡略の為め: 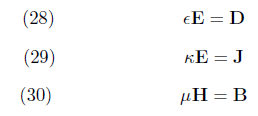 なベクトルを採用する事とすれば,電磁場の方程式は: 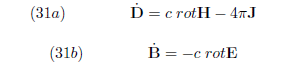 なる形となる。此の式の特徴は,最早や物体特有の性質に関する常数を含んでいない。 即ち一般普遍的の性質を帯びた方程式であるという事である。 故に此の方程式の形は,連続的の広がりを持ち且つ静止せる物体でありさえすれば,どんな不均質な又は不等方な物体にでも使用し得る形となっている。. 実際にも,此の方程式は上述の制限のもとにあらゆる場合、例えば結晶光学等に応用しても当て嵌まる事が確かめられて居る。』 以上のように、場のエネルギー保存の関係だけから、マックスエル方程式のうち時間微分を含む本質的に重要な式を導くことが出来るのは驚きである。 このことは、電磁場のダイナミックスは、電磁場自身の”力学的な”現象と解釈できることを示している。 すなわち、電場磁場で自己充足した力学系を成している。..これは電磁波が存在する可能性と関連する。 マックスウェルの方程式の内、電荷、磁荷に関する式が残っているが、それらを導くための議論が、この章の最後§10、§11に書かれている。 勿論、そこでもプランクは電場の境界及び湧き出しとして現れる存在として電荷を電場から定義づけている。 これはファラデーの発想の数学化であり、賢明な読者には説明を要しないことだろう。 第2編以降の内容第2編以降は電磁気学の各論である。 参考のため以下に、目次だけを示しておく。第2編 静的及び定常の状態 第1章 接触電圧の無い静電場 第2章 接触電圧の有る静電場 第3章 静磁場 第4章 静電磁場内の動重作用 第5章 定常電磁場 第6章 定常の場に於ける分子作用及び動重作用 第3編 準定常及び力学的の現象 第1章 閉電流に於ける準定常現象 第2章 開電流に於ける準定常現象 第3章 静止物体内の力学的現象 第4章 運動物体内の力学的現象・マックスエル、ヘルツの電気力学の適用範囲 (註: 動重作用とは、物体を動かそうとする力学的作用のことである。) これらにおいてもプランクは一貫して、エネルギーの原理に基づく論述を展開している。 (勿論、遠隔作用の立場のからの解説もなされている。) おわりに現代の電磁気学の教科書を見ると、「近接作用」(本書では「媒達作用」)という言葉は使われているものの、その中身は「遠隔作用」の影響の集積したものを「場」という言葉で置き換えているに過ぎないような記述の本が圧倒的に多いように見受けられる。私は常々、このことに疑問を感じていた。 本来のファラデー、マックスウェルの立場は決してそうではなかったはずである。 確かに「エーテル物質」のような分子的構造をもつ物質の存在を考えるのは間違っているかも知れないが、それを否定する余り、「近接作用論」の本質までも歪曲してしまうのは問題であろう。 その正体は何であれ「場」は厳然として実在するし、その場から「マックスウェルの応力テンソル」を介して近接作用を受けていることを現代の我々も否定することは出来ない。 そこで、そのことを確認するため、昔の電磁気学の教科書を辿って調べてみようと考えたわけです。 そして、20世紀前半に書かれた本書を見つけて読んだところ、私の予想通り、プランクは昔の「エーテル説」を避けながら、見事に「近接作用論」の電磁気学を展開しているのです。 本書のように一貫して、エネルギー原理から「電磁気学」の体系を教えるのは、無理があるだろうが、少なくとも、現在の多くの教科書に見受けられるように、歴史的なファラデーやマックスエルの発想を紹介せずに、電場Eや磁場Bを使うだけで、それが「近接作用論」であるかのように主張するのは問題である。(このことについては、私の別ページで説明する予定です。) 忘れ去られたこの本を紹介することにより、現代の「電磁気学の教育」に一石を投じることが出来れば、と考える次第です。 なお、同様の視点から書かれた和書としては、今井 功 氏の「電磁気学を考える」がある。 このページのトップへ |
物理教育・物理教育のページの解題・物理教育序論 ・慣性力について(慣性力序説) ・慣性力はみかけの力ではない。(慣性力続編)更新 ・慣性力についての対話(みかけの力とは?、ダランベール原理について)更新 NEW! コリオリの力について (慣性力対話 2 ) ・力はベクトルか?(力の正体をさぐる。) ・開口端で音波はどのように反射しているのか。 New! ・物理”診断テスト”と”運動についての常識概念” 物理実験・新方式の「運動法則の実験」
ご感想等 |